短尺動画の台頭、AI時代のコンテンツ戦略の進化、そしてフォロワー数に依存しないSNSマーケティング──。急速に変化するSNS環境に対応し成果を上げるには、各プラットフォームの特性を理解し、リーチやエンゲージメントを意識した柔軟な戦略設計が不可欠です。本記事では、SNS運用の第一線で活躍する小川 宗紘・平井 実咲・福島 ひかるの3名とともに、いま押さえておきたいSNSマーケティングの実践視点と未来像を探ります。

短尺動画コンテンツの台頭とアルゴリズムの影響
──2023年にSNSマーケティングの活用状況について小川さんにお話を伺いました。それから2年が経ちますが、SNSをめぐる環境の変化やトレンドについてどのように感じていらっしゃいますか。
小川:特に感じているのは、SNS上のトラフィックが大きく増加していることです。それに伴い、各プラットフォームのアルゴリズムも変化していて、現在は「動画を投稿しなければ見てもらえない」という状況が、より明確になってきていて、視聴態度や行動の変化は間違いなく起きていると思います。SNSは今や年齢を問わず多くの生活者が利用するメディアですが、もともと若年層を中心に浸透していた短尺動画の視聴習慣は、徐々に30代・40代といった上の世代にも広がりつつあるように感じます。
前回記事はこちら
──情報を受け取る手段として、動画がより重視されているのですね。具体的にはどのような動画が中心でしょうか。
平井:TikTokの台頭により、Instagramの「リール」やYouTubeの「ショート」など、各プラットフォームは15秒から1分以内の“短尺動画”を重視している印象です。一方で、これまでのような静的コンテンツではリーチが難しくなり、見てもらいたい人へ情報が届きにくくなってきていると感じています。
福島:たとえば、X(旧Twitter)も、もともとはテキスト中心のプラットフォームでしたが、現在は動画コンテンツの強化に注力しており、今後はショート動画がさらに押し出されていくのではないかと見ています。
──SNS動画の活用に力を入れた提案は多くなってきたりしているのでしょうか。その場合、具体的にどのような領域での相談が多くなってきていますか?
平井:そうですね。ただ、それは商材による部分も大きく、一概には言えないところがあります。たとえば、すでにブランドが確立されている商品と、これから認知を広げていく商品とでは採るべき施策が異なってきます。むしろ、近年はSNSマーケティングの領域が新たに広がってきている印象があります。
小川:端的に言えば、BtoB領域でSNSを活用したいという相談が増えています。そうした場合には、BtoBのビジネスマッチングに適したLinkedInをご提案することもあり、採用活動やIR(インベスター・リレーションズ)にもつながるケースがあります。企業の信頼感を発信する手段として欧米では以前から注目されていましたが、日本でもビジネス用途での活用が徐々に根付きつつあると感じています。

成果につなげるには、SNSごとの特徴を捉えておくべき
──それぞれのプラットフォームの特徴や、おすすめの活用方法について教えてください。
小川:基本的に各プラットフォームの強みは大きく変わりませんが、ここ数年で特に印象的なのはXの変化です。これはイーロン・マスク氏による買収の影響もありますし、2023年頃から急速に進化した生成AIの影響を最も受けているプラットフォームかもしれません。例えばですが、グローバルなコンテンツ流通が一層加速しましたし、AIが生成した情報やコンテンツが大量に流れるようになったことで信頼性や情報の取捨選択がこれまで以上に重要になってきたと感じます。AI生成の情報が当たり前のように流通するようになったことで、注目を集める投稿であっても「まずは疑ってみよう」という姿勢が多くのユーザーに根付いてきているように思います。
福島:Xに限らず、生活者の視点ではAIとの組み合わせによる新しい楽しみ方が増えたように感じます。たとえば、ChatGPTを使ってアニメ風の画像を生成するのがトレンドになりました。その一方で、フェイクニュースやGrokによる「ファクトチェック」のように、情報の受け取り方にも変化があり、良い面もあれば混乱を招く面もある。Xは、そうした両面が特に顕著に現れているSNSだと思います。
──Instagramについてはいかがでしょうか。
平井:これはSNS全般にも言えることですが、Instagramでは「共感性」や「納得感」が重視されていると感じます。顔の見えない相手とのやりとりであっても、共感を得られる投稿が支持されるという点は、今も昔も変わらず大切にされているところですね。先ほどお話ししたリールの活用が進んでいる点も含め、アパレルや化粧品など、上品なイメージのブランディングには適したプラットフォームだと思います。

──Xからの移行先として、ThreadsやBlueskyなどの新たなSNSも注目され始めています。こうした動きについてはどう見ていますか?
小川:確かに、Threadsの利用者は着実に増えてきています。ThreadsはFacebookやInstagramと同じMeta社が運営していますが、現時点では企業が本格的に活用している例はまだ少ないように思います。興味深いのは、同じ運営元でありながら、ThreadsはInstagramよりもラフな空気感がある点です。これは、プラットフォームごとの文化の違いとも言えます。たとえば、Xはタイムリーで強い意見を発信する投稿が多く見られる一方で、Instagramではビジュアルを重視した丁寧な表現が好まれます。Threadsはその中間に位置するような印象で、今後の動向にも注目しています。
福島:個人的には、かつての旧Twitterが「テキスト特化」、Instagramが「写真特化」としてローンチされたときのような衝撃がThreadsやBlueskyにはないため、現時点では既存プラットフォームとの差別化がやや難しいと感じています。
──日本国内における独自の動きや傾向はありますか?
小川:LINEはコミュニケーションアプリをベースにしているため、利用者数が非常に多く、既存顧客へのリーチ率も高い傾向があります。たとえば、ある商品をサンプリングするキャンペーンなどを確実に届けたい場合には、非常に有効な手段です。
平井:最近はnoteも「SNS的な文脈」で語られることが増えてきました。もともとブログメディアとしての性格が強いため、記事のボリュームが多く制作にはそれなりの工数がかかります。ただし、情報感度の高い読者層との親和性が高く、深いコミュニケーションが可能である点が特長です。note単体で頻繁にコンテンツを更新するというよりは、Xでnoteの記事リンクをシェアして誘導するなど、他SNSとの組み合わせによる運用が一般的になっています。
フォロワー数から接触機会とエンゲージメントの向上へ
──企業視点でのSNSマーケティングにも何か変化はあるのでしょうか。
小川:以前は「とにかくフォロワーを増やす」ことが、SNS運用のKPIとされることもありました。しかし、今は変わってきています。もちろん今でもフォロワー数を重視する企業は一定数いらっしゃいますが、SNSを「ファンをつくる場」「ユーザーとコミュニケーションする場」として捉える傾向は以前よりも明確に強まっていると感じます。
平井:今は「インプレッション」や「リーチ」、つまり情報がどれだけ多くの人に届いたかという指標が重視されるようになってきています。重要なのは、「たまたま情報に触れる人」をいかに増やせるかという点です。実際、投稿を見ているのが既存フォロワーなのか、それとも新規の閲覧者なのかといった割合も細かく分析しています。
福島:Z世代と言われる若者で顕著に出ているのは、アルゴリズムが届けてくれる情報で十分だという感覚です。「自分に合った情報は自然に流れてくる」という前提でSNSを利用していることが多いため、フォローする必要がないということなのかなと思います。企業アカウントも、有益な情報を継続的に発信していない限りフォローにはつながりにくいのです。この傾向は、データ分析の数値にもはっきりと表れています。
小川:なので企業のSNS施策では、接触機会を意図的に増やし、既存ファンと新規ユーザーの両方に最適化されたアプローチが求められています。既存フォロワーに喜ばれる投稿はもちろん大切ですが、同時に新規ユーザーとの接触機会を増やすための投稿も意識的に作っていく必要があります。私たちはその両面を意識しながらコンテンツ運用を行っています。
──これまでエンゲージメント率も重視されてきたと思いますが、その点についても変化はあるのでしょうか。
平井:エンゲージメントは今でも重要な指標ですが、それだけでは捉えきれない部分が増えてきたと感じています。そのため、プラットフォームに応じた接触機会の創出や動線設計の巧拙が、より問われるようになってきました。
小川:私はむしろ、「リーチを出すことと、エンゲージメントを獲得することの上手い使い分け」が今後さらに重視されるのではないかと思っています。というのも、現在はフォローしなくても情報を手軽に得られる分、タイムライン上でアカウントを認知してもらうためには、リーチを出すことは無視できません。ただし、接触した情報にちゃんと注目してもらえるか、真のファン育成につながるかは、これまで以上にクリエイティブを含むコンテンツの「質」も求められると考えます。そのためには、ユーザーインサイトを的確に捉えることも不可欠で、表層的なリーチだけでなく投稿後の分析と改善を繰り返すサイクルがますます重要になってくると思います。
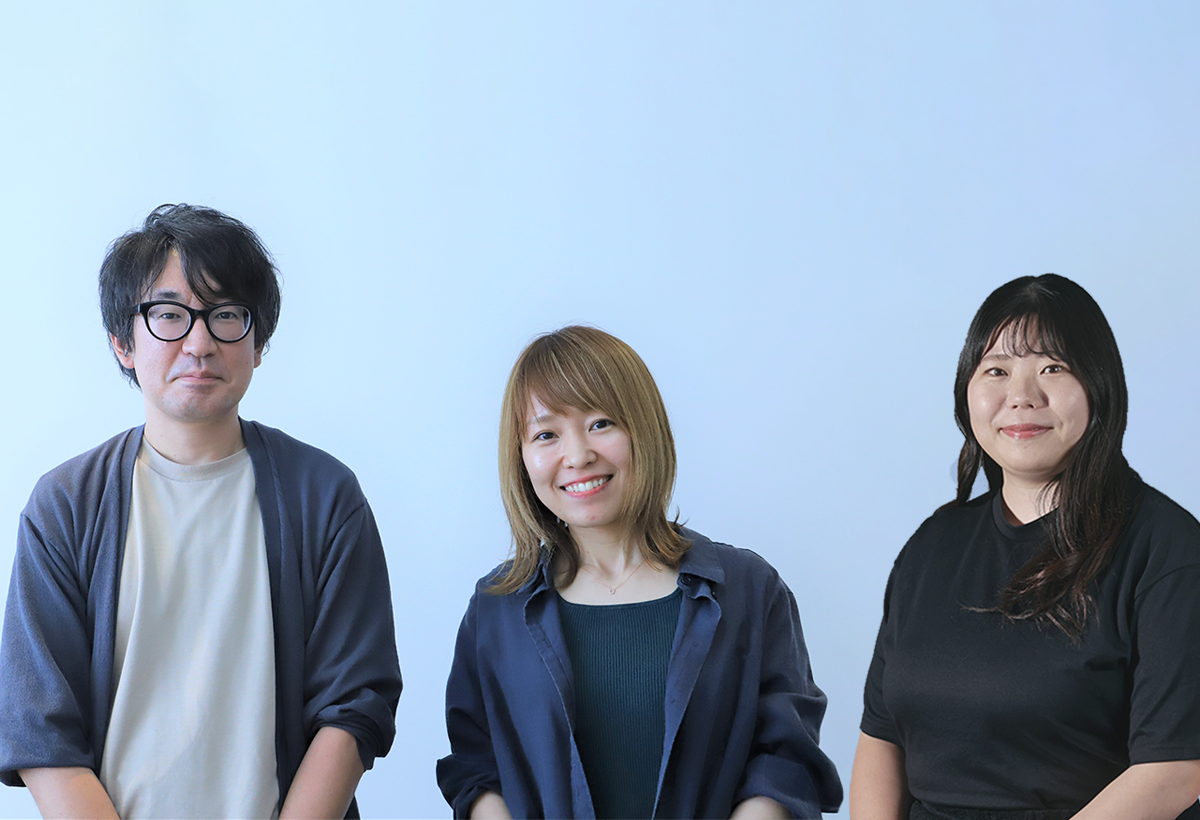
プロフィール

- 小川 宗紘
-
2013年、新卒で博報堂プロダクツ入社。
WebやXR領域を経て、2019年のSNS専門チームの立ち上げをきっかけにSNS領域に本格的にジョインし、現在に至るまでSNSの戦略プランニングから制作のディレクションを中心に従事している。SNSに関するセミナー、講演経験も多数。最も得意とするプラットフォームはInstagramとX。

- 平井 実咲
-
2021年、博報堂プロダクツに入社。
SNSを軸にしたブランドコミュニケーションの戦略設計から、コンテンツ企画・運用・分析までを一貫して担当。データと感性のバランスを大事に、数字だけでは見えないニュアンスや空気感も捉えながら、SNSを通じてブランドの魅力を最大限に引き出すことを目指している。

- 福島 ひかる
-
2023年、博報堂プロダクツに入社。
SNSマーケティングを中心に、運用だけでなくインハウス支援として運用コンサルティングまで幅広く対応。また、キャラクターを起用したコンテンツマーケティングのプロデューサー兼ディレクターの実績も多数。
